
「ノベルゲームだから、おもしろい」
ノベルゲームブランドANIPLEX.EXEが掲げるキャッチコピーである。その自負とともに送り出された作品たちはいずれも高品質で、このジャンルの愛好家たちの期待に応えてきたと言えるだろう。
そして2024年12月、最新作『たねつみの歌』がリリースされた。企画・シナリオを手がけたのは、商業的な実績がなくほとんど無名だったが、フリー・同人ノベルゲームの世界ではその実力を知られていたKazuki氏である。
『たねつみの歌』発売直前! STUDIO・HOMMAGEの『国』シリーズ全作品レビュー
彼の栄えある商業デビュー作となった『たねつみの歌』だが、これまでのANIPLEX.EXE作品と明確に異なる点がある。それは選択肢が一切ないという点だ。
小説のように文章を読み進み、時折現れる選択肢を選んで分岐するルートや複数用意されたエンディングを楽しんでいく作品……ノベルゲームの定義を問われれば、こういった模範解答があるだろう。
そこにひとつの問題が立ち現れ、たびたび議論されてきた。選択肢のないノベルゲームはノベルゲームであるのかと。
私の現在の意見は「ゲームという枠組みで開発し、ゲームという枠組みで流通させているなら、それはゲームだ。このジャンルのもっとも簡潔な呼び方なのでノベルゲームという語を用いている」というものだが、異論もあるかと思う。
ともあれ選択肢やコマンド、それらに類するシステムによる一切の分岐構造を持たない作品――まずはこの「選択肢なしノベルゲーム」という一見奇妙なジャンルの歴史を概観してみたい。
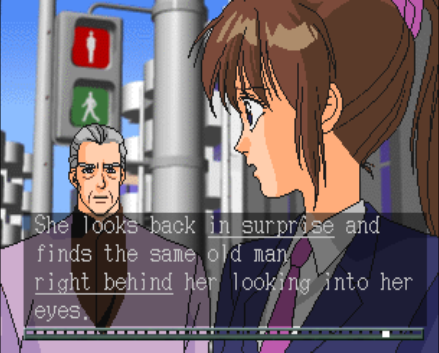
※画像はPS版(1995年)
『EMIT』(光栄、1994年)は公式にはマルチメディア英語体験ソフトと謳われた作品だが、そのプレイ感覚はまさに選択肢なしノベルゲームと分類することが可能だ*1。
本作は複数機種のPCに加え、スーパーファミコン、PlayStation、セガサターンと、当時の主要コンソールで発売された。シナリオ原案に赤川次郎氏、キャラクターデザインにいのまたむつみ氏、音楽に小室哲哉氏と各業界のトップクリエイターを招聘したことでも話題となった。
PCアダルトゲームにおいても選択肢なしノベルゲームが、90年代から多くはないものの存在した。既存の官能小説にそのままグラフィックと音楽を付けただけという例もあった。
21世紀に入るとPCアダルトゲームにもストーリー重視の波が本格的に押し寄せる。各社とも作品が長大化していく中で、選択肢なしノベルゲームはコストを抑えた実験作、コンパクト作品の受け皿としての意味が見出される。2002年にニトロプラスから発売された『鬼哭街』は同社の、そしてシナリオライター虚淵玄氏の代表作のひとつだ。2011年にはレーティングを全年齢対象(15歳以上推奨)に変更してリメイクされている。

※画像は2011年リメイク版
わずか数ヶ月で作られたという『鬼哭街』だが、「当時の基準で考えたらありえない試みだった」「分岐が存在しないので,実際は“ゲーム”じゃないんですけどね(笑)」と虚淵氏は述懐する。公式のジャンル名は「ストーリーノベル」。ショップとのやり取りもいろいろとあったようだ。
お店のほうから「何でもいいから,選択肢をつけてくれ」というオーダーが来たりもしましたね。いわゆる“ムカデ分岐”というヤツで、「バッドエンドとグッドエンドがあるだけでもゲームだと言い張れるから!」と。
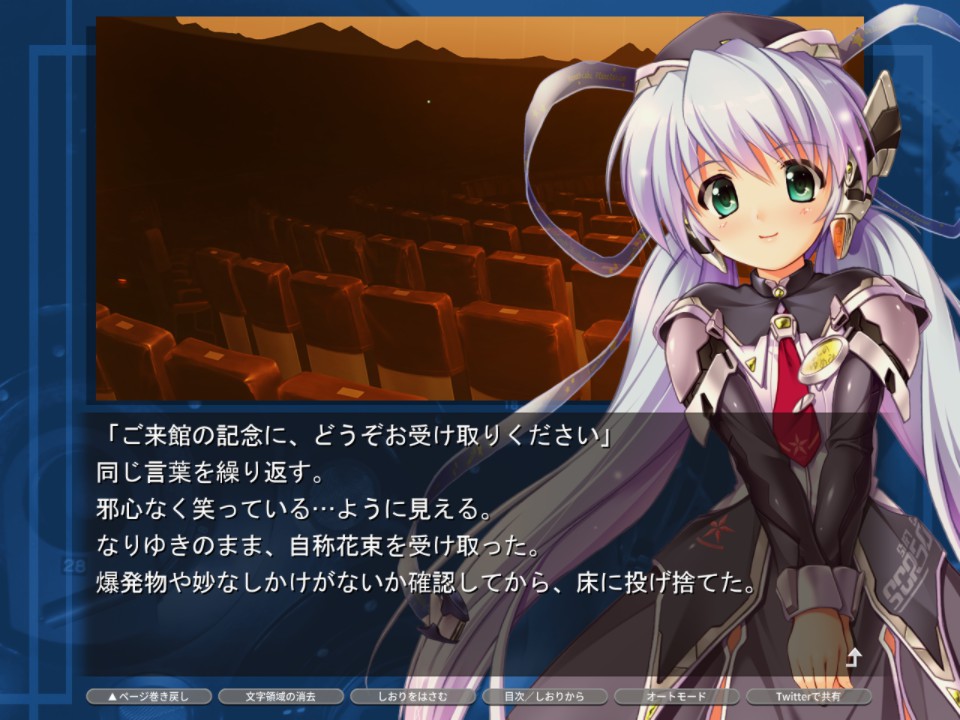
※画像は2016年PCHDエディション
2004年にはビジュアルアーツが「キネティックノベル」というジャンルを提唱し、第一弾の『planetarian 〜ちいさなほしのゆめ〜』がKeyブランドより発売される。『CLANNAD』に続く全年齢対象の作品だ。当初はまださほど一般的ではなかったダウンロード販売のみだったが、ネット環境さえあれば全国どこからでも購入できたのはノベルゲームメーカーにとっては革新的な試みだったと言えるだろう。やがて販路が拡がり、PlayStation 2やPSP、近年になってもNintendo Switchへの移植が行われている。
2005年にocelotブランドから発売された『神曲奏界ポリフォニカ』は大幅なメディアミックスが行われた。ゲーム版よりも同一世界設定を元としたシェアード・ワールドのライトノベル群が有名になった。
複数のブランドで展開していたキネティックノベルは現在もKeyにおいて続いており、『LOOPERS』『終のステラ』『プリマドール』といった話題作が立て続けに発表されている。
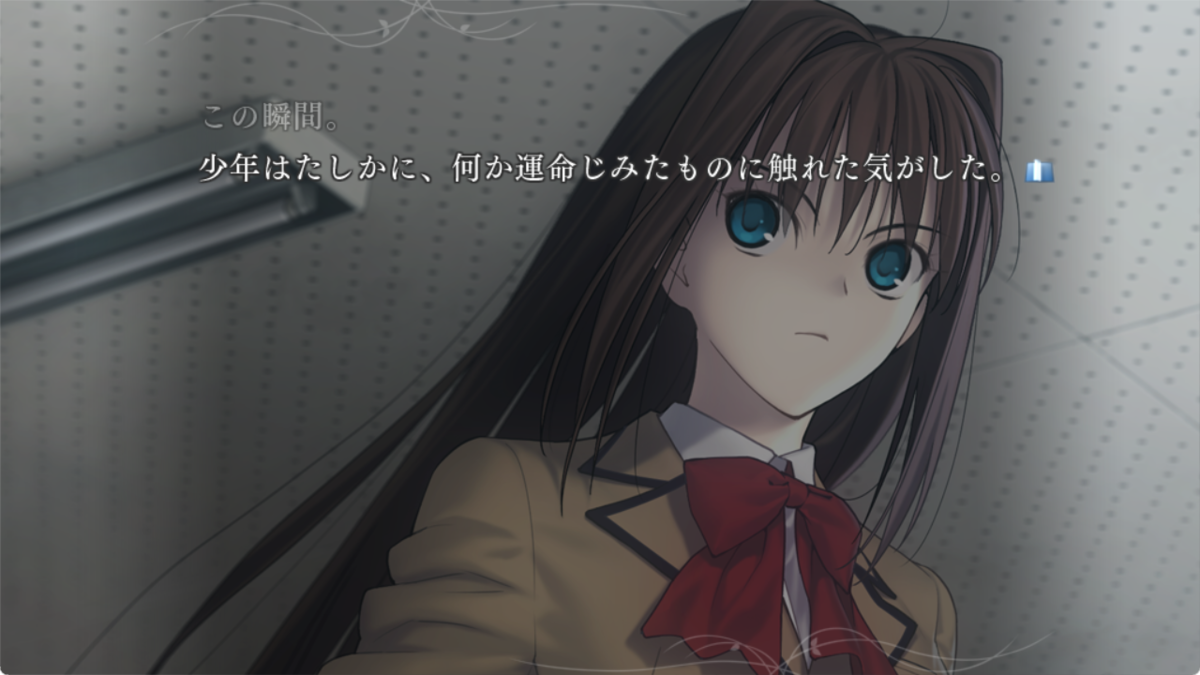
フルプライスの選択肢なしノベルゲームも稀ながら存在する。Fateシリーズでノベルゲーム業界のトップチームとなったTYPE-MOONが2012年に発表した『魔法使いの夜』は、シナリオライター奈須きのこ氏の未発表小説を元にした作品。ストーリー以上に常識を越えた演出力でノベルゲームに新たな記念碑を打ち立てたが、これが実現できたのはTYPE-MOONと奈須氏のブランド力あってのものだろう。ただし本編クリア後の番外編には選択肢ありの小話が用意されている。
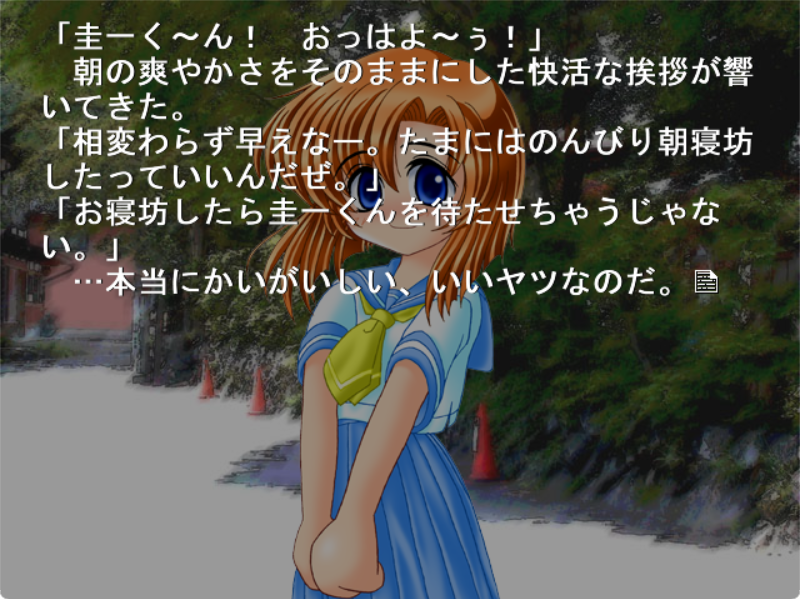
アマチュアの世界では、これらとは違う流れが起きた。特筆されるのは『ひぐらしのなく頃に』で、2002年夏に第1作目「鬼隠し編」が発表される。
この当時は無名だったが2004年に口コミでブレイク。一切の選択肢がないが連作形式を活かし、次作が頒布されるまでの間にプレイヤーにゲーム外で推理させるという構造が革新的であった。漫画、アニメをはじめ多数の商業展開が行われ、現在では同人ノベルゲームの金字塔という評価を確固たるものにしている。
他にもフリー・同人ノベルゲームでは選択肢なしノベルゲームが無数に作られている(私も著作権切れの名作を利用した作品をいくつか作ったことがある)。コスト削減という思惑はあるにせよ、商業的な制約が一切ないため、作者は自由に思うままのストーリーを形にすることができた。選択肢がないことが逆に自由をもたらすというのが面白いところである。「ゲームではないかもしれないが、それはそれ」というわけだ。
Kazuki氏が取り組んできた一連のフリー・同人ノベルゲームもこの流れの中にあった。プロデューサーからのオファーに対しても「選択肢のあるノベルゲームはやりませんし、やりたくないとお伝えしていました」と、その強いこだわりをインタビューで明かしている。
『鬼哭街』がそうであったように、選択肢なしのノベルゲームはかつて流通には歓迎されづらかった。「ストーリーノベル」や「キネティックノベル」というジャンルを標榜したのは、作り手の立場でもゲームと称することが憚られていたからに他ならないだろう。近年はアダルトゲームのロープライス作品に選択肢なしのノベルゲームが増加しているが、レーティングと知名度の問題もあってインパクトは乏しい。
この流れを踏まえると、エンタメ業界きっての母体を持ち、「ノベルゲームだから、おもしろい」を掲げるANIPLEX.EXEがKazuki氏を起用し、彼の希望どおりに選択肢なしのノベルゲームを作り上げたことには、既存の在り方を打破したいという気概を感じさせる。
ジャンル ノベルゲーム
これが『たねつみの歌』公式サイトに記載されている。我々が作っているのは間違いなくノベルゲームであるのだという堂々たる宣言だ。選択肢の有無などはもはや問題とは捉えていないのである。
ANIPLEX.EXEは「クリエイターとの作品制作を通して、ノベルゲームの魅力を広めていくプロジェクト」だという。ここから読み解けるのはクリエイターファーストの精神であり、何よりもシナリオライターの個性を最大限に活かすということだ。『ATRI -My Dear Moments-』『徒花異譚』『ヒラヒラヒヒル』はいずれも書き手の才気煥発された作品だった。
今回ラインナップに加わった『たねつみの歌』もブランドの看板に恥じない、Kazuki氏の魅力が濃密に詰まったノベルゲームに仕上がっていた。次回以降に詳しく論じてみたい。
『たねつみの歌』レビュー:家族愛を歌い上げた2024年を代表する国産ノベルゲーム
© KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.
© NITRO PLUS
© VISUAL ARTS / Key
© TYPE-MOON All Rights Reserved.
© 07th Expansion
*1:チャプター毎に内容に関する出題が用意されているが解答必須ではなく、後の展開にも影響は及ぼさない。
