
よくぞこの人を商業の舞台に連れて来てくれた――
その第一報を目にした時に、まず抱いた気持ちがそれだった。
『ATRI -My Dear Moments-』『徒花異譚』『ヒラヒラヒヒル』を送り出してきたノベルゲームブランドANIPLEX.EXEが次なるタイトルとして発表したのは『たねつみの歌』。企画・シナリオを務めるのはKazuki氏。『国』シリーズの制作者――しばしばこのように紹介されるが、初耳という人も多かったことだろう。
Kazuki氏は個人サークルSTUDIO・HOMMAGE(スタジオ・おま~じゅ)を立ち上げ、これまでに何本もの良作ノベルゲームを発表してきた。フリー・同人ノベルゲーム界では高い評価を受けてきた、知る人ぞ知るクリエイターなのだ。
もしも商業の舞台に行ったとしても必ず受け入れられる――私はそう疑っていなかったし、同じ考えのノベルゲーム愛好家は少なくなかったはずである。ANIPLEX.EXEプロデューサーも「近年で滅多にない感動」をしたといい、その熱量のままオファーしたということがインタビューで明かされている。
新作『たねつみの歌』制作時に掲げた3つのテーマとは? アニプレックスのノベルゲームブランドANIPLEX.EXEの制作論【島田Pインタビュー】 - 電撃オンライン
そこで今回はKazuki氏の活動の根幹を成している『国』シリーズとは何なのか、全作品を紹介していきたい。
『みすずの国』
運が悪い人はいる。でも、私じゃないって思ってた。
天から力を授かったとされる天狗。神通力が発現していることが検査で発覚し、法律上日本国民から外され天狗と認定されてしまった少女美鈴は、京都丹波の山奥の特別自治領区、通称天狗の国に向かわなければならなかった――シリーズ第一弾の『みすずの国』は、そんな魅力的なオープニングから世に送り出された。
本作を初めてプレイした時、真っ先に感じたのがその巧緻な文章だったことをよく覚えている。地の文は情緒豊か、台詞はリズム良く、ところどころに教養も滲み出る――フリー・同人ノベルゲームのシナリオライターにはしばしば「野生のプロ」と形容したくなる人が存在するが、Kazuki氏もそのひとりだった。

人間界とのギャップに四苦八苦する美鈴と、鞍馬の国の姫・ヒマワリとの交流をメインに物語は進行する。ただただ平凡な少女と、生まれついての貴族であり圧倒的な才の持ち主。こういった構図は何十年も前の少女漫画から描かれているが、天狗の国という舞台設定が妙味をもたらしている。
同じ国のようでそうではない異郷、そこに身を投じざるを得なかった美鈴の苦労は、単なる現代ものでは描きがたい重さがある。それでも健気さを失わない美鈴のキャラクターこそが本作一番の美点だ。ラストにおける彼女の気概と挑戦は、胸のすく清涼感に満ちている。エンディングもふたりのこれからの関係性を明示して、実に爽やかだ。
次に紹介する長編『キリンの国』のプロモーション作品という位置づけでもあり、プレイ時間は2時間程度。現在リメイクが進行中のようだが、それの完成まで待つことはない。シリーズの入門編としてぜひプレイしておこう。
『キリンの国』
「ここから抜け出そう。綺麗なものを見にいこう。わくわくすることをしようぜ」
天狗の国、鞍馬特区から追い出された身であるキリンと「超過者」である圭介。ある日、ふたりのもとに一通の手紙が鞍馬特区から届く。それは鞍馬のお姫様、ヒマワリからの招待状だった――『みすずの国』は少女コンビだったが、今度は少年コンビの物語となる。
法律の制約上、遠出もままならない圭介を屈託なく「一緒に行こう」と誘うキリンに対し、圭介は何だかんだと言いながら付いていく――この導入部だけで、ふたりの適度な距離感の友情が伝わってくる。そもそも野郎ふたりで夏の旅というのが、もう抜群にいいわけだ。
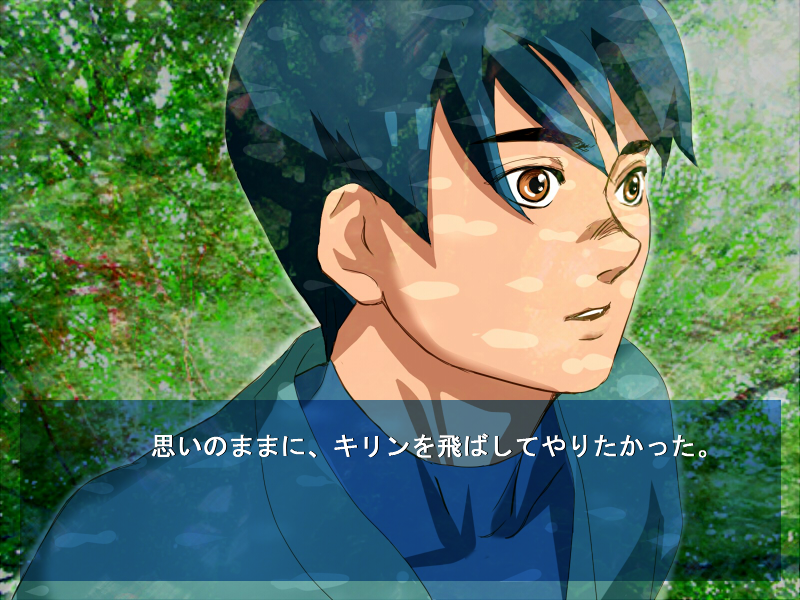
鞍馬特区への密入国を経て、ふたりは様々な人々に出会う、温かな交流あり、いけすかない敵役とのいざこざあり、そして『みすずの国』で強烈な印象を残したヒマワリとの邂逅あり――登場キャラクターは相当に多いのだが(立ち絵は合計1,000枚にもなるそうだ)、誰もが皆、個性的な存在感の持ち主。心地よい会話、食事シーン、独特の風俗、神通力による鍔迫り合いなど、心理描写はもちろん、あらゆるキャラクター描写においてKazuki氏の卓越した技量が表れている。
本作のテーマは、少年たちの夏の一幕だ。ヒマワリとの胸が熱くなるようなラブコメとか、閉鎖的な天狗の国を相手取っての大立ち回りなどはない。圭介とキリンの、どこまでも青く、まっすぐで、鮮烈な夏。『みすずの国』がそうだったように、本作の美点は何より主人公。圭介は第一印象、いささか軽薄そうに見えるが、人情と優しさ、強さにあふれた“男”なのだ。
本作は第10回ふりーむゲームコンテストの最優秀賞を受賞した。それだけでなく『みすずの国』もノベルゲーム部門金賞でダブル受賞を果たしている。この快挙もあってKazuki氏の評判は一挙に高まっていった。
『雪子の国』
やがてくる冬は、最後の冬になる。
少年と少女でいられる最後の時を、鮮烈に駆ける、今を生きる物語。
シリーズ初の有料作品となる『雪子の国』は、これまでのフリーゲーム2作品とは、その雰囲気をガラッと変えてきた。
『みすずの国』では、異国におけるひとりの少女の決意を。『キリンの国』では、やはり異国におけるふたりの少年の強さを。日本国内にあって独自の歴史と価値観を紡いできた天狗の国。我々の住む世界と大きくかけ離れ、いけ好かない空気とどこか温かい空気が同居していた異界。その異界の空気の描写こそが本シリーズの根幹であり、だからこそ足を踏み入れた彼ら、彼女らの健気なキャラクターはより際立つ仕組みになっていた。
そんな天狗の国は、戦争の結果すでに解体され、天狗たちも「帰化生」として各地に散っていた――この思い切った舞台設定には心底驚いたが、設定ひとつで良作たりうる作品というのは確かにある。『雪子の国』も間違いなくその類だった。

地方活性化と青少年教育を兼ねたホームステイ制度・故郷留学。東京から遠く離れた海沿いの町にやってきた主人公の神崎ハルタは、そこで様々な人々や不可思議現象と出会い成長していく――ストーリーの大筋はこのようなものだ。
住み慣れた場所を離れ異郷に飛び込むというのは前2作と同様だが、ヒロインが登場するという決定的な違いがある。すなわち作者はラブストーリーに挑戦したのだ。
天狗、帰化生の東雲雪子。気が強く、「才貌両を備えたパーフェクツな雪子ちゃん」などとちょくちょく自慢も入る、自主自立精神の強い少女。そして『みすずの国』の舞台でもあった愛宕の、戦争で敗れた国の出身――このキャラクター設定から、我々の住む世界の諸問題を想起しない者はいないはずである。
前2作はファンタジーの趣が強かったが、『雪子の国』はきわめて現実的だった。それはそうだろう。恋愛とはファンタジーではなく、どこまでも現実でなければならない。
ハルタと雪子は、あくまで独自に自身の魅力を見せる。それが結果的にふたりの繋がりに説得力を持たせている。積極的に寄り添い干渉するばかりが、恋愛を成功させるプロセスではない。男女が結ばれるのに、劇的なイベントは必要ない。
従来のノベルゲームにおける恋愛描写は、美少女ゲームにせよ乙女ゲームにせよ、多くは男性主体だろう。そのいずれでもない『雪子の国』だからこそ対等な、ニュートラルな男女の恋愛描写が成立しえたのではないか。
プレイ時間は20時間ほどになるだろう。シリーズの美点である叙情性に加え、新たに爽やかな男女の絆を見せてくれた。3作目にしてそのクオリティは頂点に達したこと疑いなかった。
しかしKazuki氏はさらなる挑戦に打って出た。
『ハルカの国』
明治、大正、昭和、そして平成へ――
ハルカとユキカゼ、二人が歩いた道のり
100年のビジュアルノベル
Kazuki氏が現在全霊で取り組んでいる、『国』シリーズの総仕上げとなる連作形式の大長編『ハルカの国』。この開発にあたってはクラウドファンディングが活用され、個人開発のノベルゲームとしては破格の累計270万円もの調達に成功した。もちろん私も支援させてもらっている。
全6作が予定されており、現在までに「明治越冬編」「明治決別編」「大正星霜編」「大正決戦編」と第4作まで完成している。ここでは体験版として丸々公開されている「明治越冬編」について触れたい。

これまでのシリーズでも顔を出していた賢狼ハルカ。彼女はどう生きていたのか、そして彼女が残した因果が現代までどのように繋がっていくのか。100年の物語は明治の冬から始まる。
語り部は新政府に仕えながら剣の腕を磨いていた、狐の化けであるユキカゼ。彼女のキャラクターが抜群にいい。気持ちいいほどの刀馬鹿だ。意気軒昂としてハルカの元に乗り込むも圧倒される一連の描写は、本体験版前半のハイライト。ユキカゼと対極的なハルカ、その存在感の大きさがこれでもかと凝縮されたシーンだが、かといってユキカゼの株が下がるわけでもなく。この直情的なキャラクターは何より主人公にふさわしいと言える。
後半は奥深い森での越冬が、実に綿密に展開される。何ものも抗えない凶暴な吹雪の中、ユキカゼは自分を見つめ直し、ハルカの本質を観察しようとする。厳しすぎる環境のはずが、これもユキカゼのキャラクターのおかげだろう、どこか安心して読める。
しかし終盤、たったのワンシーンですべてを持って行かれる。ああそうだ、私たちは現代ではなく明治を見つめているのだ――と誰もが再認識させられるだろう。
また本作の注目すべき点は、性というものをほとんど感じないということ。
『みすずの国』では、ひとりの少女の健気さを。
『キリンの国』では、ふたりの少年の熱さと爽やかさを。
『雪子の国』では、少年と少女の情愛を。
明確に男性と女性を描いていたのだが、ユキカゼもハルカも化けということもあってか、非常に中性的なキャラクターだ。
性をめぐる描写は、現代のもっとも重要な課題のひとつ。総合的メディアであるゲームは、むしろ率先してこの課題に向き合わねばならない。現代のゲームはシナリオもアートもシステムも、性の多様性というものを無視することはできない。
『ハルカの国』はジェンダーレスな作風だ。性に囚われない個性がそこにある。シナリオはファンタジーなのだが、キャラクターはきわめて現代的。このふたりの化けが、性とは離れたところでどのような物語を紡ぐのか――体験版を気に入ったなら、その続きもぜひプレイしてほしい。
きっと『たねつみの歌』は多くのプレイヤーを獲得する。そのプレイヤーたちがいよいよ『国』シリーズに手を伸ばそうという時、本記事がガイドとして役立つことを願ってやまない。
© STUDIO・HOMMAGE